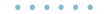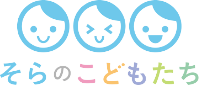「なんば歩き」はご存知ですか?
「なんば歩き」とは、右手ー右足、左手ー左足を同時に出す歩き方です。語源は「難場」すなわち「難儀な場所」を意味し、そういう場所では、自然と膝の上に手を添えて歩くことになるので、右手と右足が同時に出ることになったそうです。
江戸時代は、このなんば歩きが主流だったようで、浮世絵に出てくる大名行列、能や歌舞伎の様子でもよく見るとなんば歩きで歩く姿が残されています。
江戸時代後期からの西洋文化の流入で、なんば歩きは次第に現在の歩き方に淘汰されて来ました。そもそも西洋人は靴の文化で、しっかりとかかとから地面を踏みしめてつま先で蹴りだす歩き方をします。日本人はぞうりをはいてすり足で歩くことが主流でした。剣道や相撲の基本もすり足ですね。
陸上競技の2003年世界陸上パリ大会で、末続慎吾選手が200メートル決勝で20秒03の記録で銅メダルと獲った時、記者会見で「なんば歩きを意識した」と発言して一躍注目されました。
コーディネーショントレーニングの一環で、当園では、後ろ向きに歩いたり、なんば歩きをしたり、いろいろな歩き方を試して脳に刺激を与えています。普段と違う動作をすると脳が活性化されるそうです。人間の体って不思議ですね。
「なんば歩き」とは、右手ー右足、左手ー左足を同時に出す歩き方です。語源は「難場」すなわち「難儀な場所」を意味し、そういう場所では、自然と膝の上に手を添えて歩くことになるので、右手と右足が同時に出ることになったそうです。
江戸時代は、このなんば歩きが主流だったようで、浮世絵に出てくる大名行列、能や歌舞伎の様子でもよく見るとなんば歩きで歩く姿が残されています。
江戸時代後期からの西洋文化の流入で、なんば歩きは次第に現在の歩き方に淘汰されて来ました。そもそも西洋人は靴の文化で、しっかりとかかとから地面を踏みしめてつま先で蹴りだす歩き方をします。日本人はぞうりをはいてすり足で歩くことが主流でした。剣道や相撲の基本もすり足ですね。
陸上競技の2003年世界陸上パリ大会で、末続慎吾選手が200メートル決勝で20秒03の記録で銅メダルと獲った時、記者会見で「なんば歩きを意識した」と発言して一躍注目されました。
コーディネーショントレーニングの一環で、当園では、後ろ向きに歩いたり、なんば歩きをしたり、いろいろな歩き方を試して脳に刺激を与えています。普段と違う動作をすると脳が活性化されるそうです。人間の体って不思議ですね。